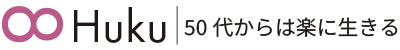こんにちは、ブログ管理人のハッチです。
若い時は多少寝不足でも回復できた体が、今は少し無理をするとすぐに不調を訴える。
肌の乾燥や気分のムラ、夜中に目が覚めるなど、これまで気にしたこともない変化に戸惑うことが増えました。
そんな時、「女性ホルモンのゆらぎ」という言葉に出会い、気になりはじめたのが大豆イソフラボンです。
雑誌やテレビでも「更年期によい」と言われるけれど、正直、仕組みはよく知らなかったんです。ただ、「昔から日本人が食べてきたものなら、まずは試してみよう」と思い、少しずつ食生活に取り入れはじめました。
大豆イソフラボンってなに?エクオールとの関係

大豆イソフラボンは、大豆などの豆類に含まれるポリフェノールの一種。
体の中で「ダイゼイン」という成分が腸内細菌によって分解されると、「エクオール」という物質が作られます。
このエクオールが、女性ホルモン(エストロゲン)と似たような働きをすることから、「植物性エストロゲン」とも呼ばれています。
つまり、大豆を食べることで、女性ホルモンをサポートするような効果が期待できるというわけです。
ただし、すべての人がエクオールを作れるわけではありません。
日本人の約2人に1人は体の中で作れないとも言われています。
これは腸内環境の違いや、普段の食生活が関係しているそう。
「同じ納豆を食べていても効果を感じにくい人がいる」のは、こうした体質や腸内バランスの違いによるのかもしれませんね。
私が「大豆」を意識して食べはじめたきっかけ
更年期のはじまりを感じたのは、45歳を過ぎたころ。
なんとなくイライラする日が増え、肌の調子も不安定。
薬やサプリに頼る前に、まずは「食べること」で整えようと考えました。
朝は納豆とみそ汁、夜は冷奴や豆腐の味噌鍋をよく作るようになりました。
コンビニではコーヒーの代わりに豆乳を選ぶことも。
そんな小さな積み重ねでも、なんとなく気分の波が穏やかになり、体の軽さを感じる日が増えました。
「昔ながらの和食って、理にかなってるのかもしれない」——そう感じた瞬間です。
特別なことをしなくても、日常の中に大豆はたくさんあるんですよね。
無理なく続ける「大豆イソフラボン」生活
大豆イソフラボンは、一度に大量に摂るよりも“少しずつ毎日”が効果的だそうです。
吸収後、数時間で半減してしまうので、1日の中で2〜3回に分けて摂るのがおすすめです。 たとえば、
- 朝:納豆ごはん
- 昼:豆腐入りみそ汁
- 夜:豆乳スープやきな粉ヨーグルト
こうして見ると、特別な準備をしなくても、自然に取り入れられる食材ばかり。
スーパーやコンビニで手に入る“庶民派の健康食”といえるかもしれません。
気をつけたい“とりすぎ”とバランスの話

「体にいい」と聞くと、つい多めにとりたくなるのが人の性。
私も一時期、毎日豆乳ばかり飲んでいた時期がありました。
すると、なんとなく体が重く感じたり、肌の調子がかえって不安定になったような気がして、少し反省。
調べてみると、大豆イソフラボンは1日あたり70〜75mgが上限の目安だそうです。
みそや納豆、豆腐などの食品だけでこの量を超えることはほとんどありませんが、サプリや健康食品を併用するとオーバーしがち。
「無理せず」「続けられる量で」——それくらいの感覚で、バランスを保つのがいちばんだと思います。
腸内環境とエクオールの関係
エクオールを作るには、腸の中にその働きをする細菌が必要です。
つまり、腸が整っていないと、大豆を食べてもエクオールが作られにくいということ。
私は野菜やきのこ、海藻など、食物繊維の多い食材を意識してとるようになりました。
便通が整うと、気分まで軽くなる気がします。
腸は「第二の脳」と言われるだけあって、体と心のバランスにも深く関わっているんですね。
まとめ|食べることで、自分を整える
更年期やゆらぎの時期は、誰にでも訪れる自然な変化。
その波を完全に止めることはできなくても、「自分を整える」意識をもつだけで、ずいぶんとラクになります。
大豆イソフラボンは、サプリよりも日々の食事の中で自然に取り入れるのがいちばん。
納豆をひとパック足す、豆乳を選ぶ、みそ汁を丁寧に作る。
そんな小さな工夫の積み重ねが、心と体をやさしく支えてくれる気がします。
食べることは、生き方そのもの。
体にいいものを“おいしく、無理なく”続けていく——
それが、50代の私なりの「整える」方法です。